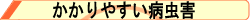 |
| 病気 特になし・害虫 カイガラムシ ハダニ |
 |
●一年を通して直射日光に当てないようにします
●乾燥に弱いので暖房や冷房の風の直接当たる場所には置かない
●耐寒気温は最低8℃以上。ホウライシダなど日本原産種は0℃くらいまで耐えます |
 |
| 繊細でさわやかな感じのする羽毛のような細かい葉とその葉のついている枝(葉柄【ようへい】といいます)の黒褐色のコントラストも美しいシダに近い趣のある観葉植物です。草丈もそれほど大きくならず明るい日陰のような場所を好みますので、室内で育てるグリーンとして最適です。手のひらにのるくらいの小さな「ミニ観葉植物」としても人気があります |
| 原産は世界中の熱帯〜温帯までで約200品種が分布しています。細かい葉が魅力ですが中には葉の大きなものや葉柄に沿って行儀よく2列に葉が並ぶものなどもあります。アジアンタムの語源はギリシア語で「湿っていない」という意味ですが、これは葉に水がかかっても水をはじいて濡れないところからきているという説があります |
| また、葉の裏に茶色いぶつぶつがたくさんできることがありますが、これは病気や虫ではなくシダ植物にできる「胞子嚢【ほうしのう】」という胞子が入っている袋なのでほおっておいても大丈夫 |
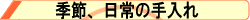 |
| 乾燥に弱く葉が痛みやすい植物です。一度痛んでしまった葉は元に戻らないので枯れた葉はこまめに取り除くようにしましょう。葉がほとんど枯れてしまった枝は根元から切りとってしまいましょう。生育期ならどんどんと葉がでてきます |
| 葉の上にキラキラと何かが這ったような跡が残っていることがあります。これはナメクジが通ったあとで植物にナメクジが付いている証拠です。新芽など軟らかいところから食べられてしまいますので見つけ次第ハシなどでつまんで捕りましょう。ナメクジの誘殺剤(ナメクジを誘って駆除する薬。ゴキブリでゆうホウ酸団子みたいなもの)が、なかなか良いものも(手で直接触らなくて良いタイプとか)出ているのでベランダなどで育てるばあいは使用することをおすすめします。ホームセンターや園芸店で市販されています |
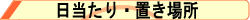 |
| 一年を通して直射日光には当てないようにします(日射しで葉が焼けてちりちりになってしまうため)。室内の明るい場所などが最適な場所です。室内でも奥まった場所や完全に日陰になるような場所での栽培は適しませんので置かないようにしましょう |
| 乾燥に弱い植物で、室内でエアコンの風に直接当たるような場所でにおいて置くと葉がちりちりになって枯れあがってしまいます。空気中の湿度が高い方がよく育つので、水やり以外にも一年を通してこまめに霧吹きで葉や茎に水をかけてあげるのが上手に育てるコツです |
| 寒さには弱く冬は最低8℃以上の気温が必要です。(例外として日本産のホウライシダなどは0℃以上)ベランダで育てている場合は冬は室内に取り込み、室内の窓際などで、レースのカーテン越し程度の日光を当てて育てます |
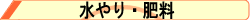 |
| 土の乾燥を嫌い水切れしやすく水が切れると葉がちりちりに枯れてしまいます。土の表面が半乾きになってきたら(土の表面がまだ湿っているうちに)たっぷりと与えます。特に夏場は乾燥しやすく枯らしやすいので朝と夕方の2回水を与えた方がよいでしょう。冬は生育期に比べると水やりの回数は少なくしますが、それでも土の表面が乾いたらたっぷりと与えるようにしましょう |
| 肥料は濃いものは厳禁です。根を傷めてしまいます。生育期は月に2回薄めの液体肥料(草花に与えるのと同じ濃さでよいでしょう)を与えます。冬は必要ありません |
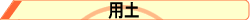 |
| 水はけの良い土が適しています。赤玉土(小粒)5:腐葉土3:川砂2の割合で混ぜた土を使用するか、市販の「観葉植物の土を使用するなら、できるだけ水はけをよくするため川砂を1割程度混ぜましょう |
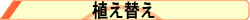 |
| 植え替えは鉢の大きさや品種によって若干異なってきますがだいたい2年に1回くらいが目安です。鉢の底から根が出てきたり、株元が混み合ってきて葉の色が薄くなるような症状が現れたときが植え替えの目安になります。適期は春から秋にかけて行います |
| 鉢から抜いた株はまわりの土を3分の1ほど落として小さなものなら一回り大きな鉢に、大きなものなら株分けを行って(その場合は今まで植えていたものと同じ大きさの鉢に一株ずつ植えます)新しい用土で植え替えます |
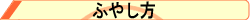 |
| 株分けでふやすことができます。大きくなった株は植え替えと同時期に行います。株元にナイフなどで切れ目を入れて手で2〜4株に裂きます。芽が出るまで乾かさないように日陰で管理します。芽が出たら通常通りの管理に戻します |